最近Qiitaの記事をまったく投稿していません。
他のサービスで情報発信をすることも一時期考えた事がありました。
ですがこのサイト以外で記事を投稿することに対して価値を感じなくなってしまいました。
なぜ私がそう思ったのか・・・
いい機会なので言語化して語りたいなと思ったので、まとめてみました。
記事に対して価値をつけるということ
インターネットには数え切れないほどの情報があります。
この記事も普通に検索してたどり着くのは到底難しいでしょう。
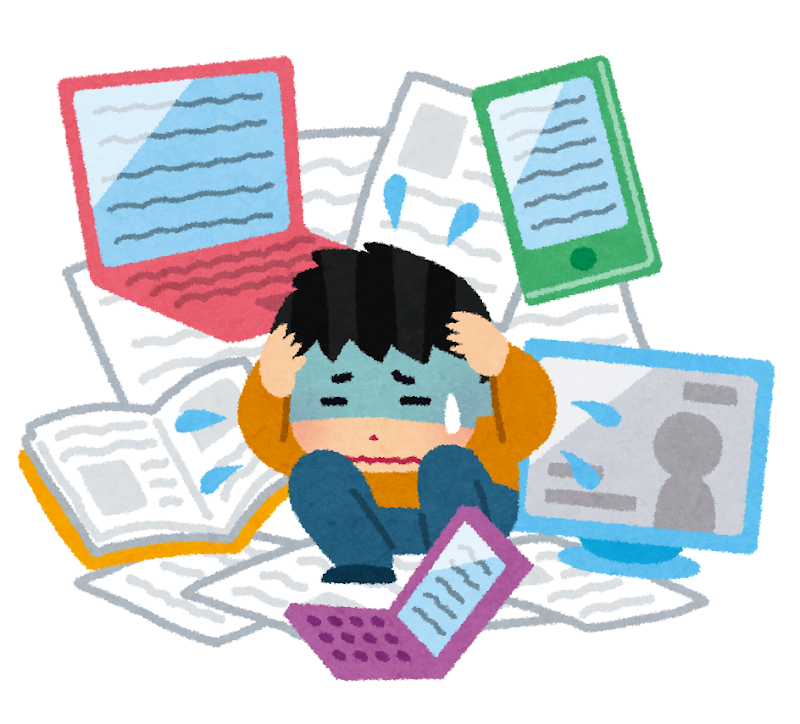
だからこそ、いま情報発信する記事には、検索流入以外の「付加価値」が必要です。その価値は、「情報」を単なるデータではなく、「鮮度」と「資産」、「知名度」という視点から捉え直すことで見えてきます。
情報の鮮度とは
かつては、技術記事の例だと新しい技術やライブラリの登場時に、その「使い方」をいち早く分かりやすくまとめることに大きな価値がありました。しかし、AIは瞬時にインターネット上の最新情報を収集し、要約できます。
AIに負けない「情報の鮮度」とは、「AIがまだ学習していない、あるいは生成できない新しい知見」のことです。
- ニッチな鮮度: 特定のニッチな環境下でのみ発生するトラブルシューティング、または最新プレリリース版の機能検証など。Web上のデータが少ない領域です。
- 現場の鮮度: 企業の特定の事情(セキュリティポリシーや既存システムとの連携など)が絡む、生々しい実装の失敗と成功の経験。これは現場にいる人間にしか知り得ない情報です。
QiitaやNoteで多くの「いいね」を集める一般的な情報は、すぐにAIに追いつかれます。だからこそ、今後はこの「現場の鮮度」こそが、技術ブログの核となります。
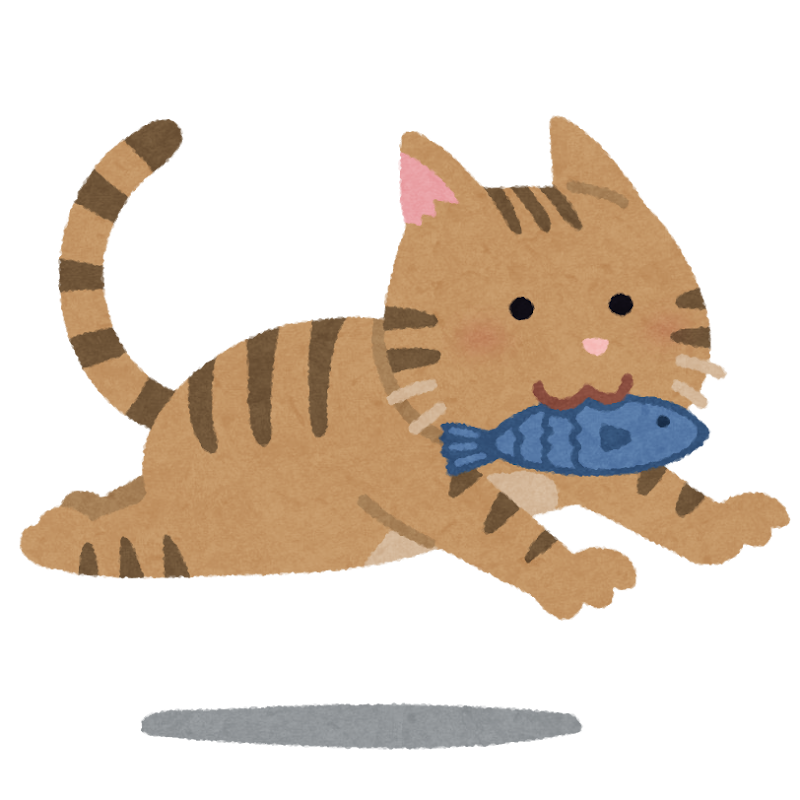
また一般的に見られるニュースサイトなどありますが、SNSのほうが情報が早いことが多いです。
このまとめサイト本当に必要・・・?みたいな記事も実際には存在しています。
情報が散乱していて読んでも意味をなさないことがあったり、情報源として正確性にかけている物が多くあります。
YouTubeもそうですね。リアル性を求めるなら当日起きたことを語るYouTubeライブのほうが情報集めやすかったりします。
私が記事にするときは情報の鮮度が極端に新しいもので世の中に出回ってない事でない限り、書きたくないというのがあります。
検索のアルゴリズムだとインプレッションが多いものが有利に働き上位に表示されるでしょう。
理想論として一番最初に記事をまとめて多くの人に見てもらえるのが理想です。
がそんな簡単にはいかないです。
また鮮度重視だと短期的には読まれますが、長期で読まれなくなることも懸念されます。
次で語る「資産」に関連します。
情報の資産とは
私がプラットフォームの投稿に価値を感じなくなった最大の理由が、この「資産性」です。
情報の鮮度が「短期的な価値」なら、資産は「長期的な価値」です。

鮮度の高い記事は瞬間的にアクセスを集めますが、時間とともに検索結果の奥へ沈んでいきます。
よくYouTubeやSNSなどおすすめに出てくる投稿は、話題性がある新しい情報にあたりますが、時間が経つと表示されなくなるのと同じです。
しかし、体系的で普遍的な知識、深い解説、そして何より「どこにもない独自の視点」で書かれた記事は、時間が経っても読者に求められ続けます。
- プラットフォームの投稿:どんなに良質な記事を書いても、それはプラットフォームのドメインに紐づく「間借りした資産」に過ぎません。サービス終了や規約変更のリスクもあります。また何かしらの理由でアカウントバンを食らった場合、過去に書いた資産がゼロになるのと等しく、復旧作業が難しいです。
- 独自ドメインブログの記事:時間をかけて良質な記事を投下することで、このドメイン自体に信頼性とSEOパワーが蓄積します。これはまさに「自分の土地に建てた永続的な資産」です。
記事を書く労力は同じです。ならば、その労力を永続的な「自分自身の資産」として積み上げるのが、最も合理的な選択だと考えました。
どんな記事が資産になるのか
次にどんな記事が資産になるか考えました。
- 検索エンジンやAIが再現できない、人間の「文脈」と「感情」が詰まった情報
- 実体験とメリットが語られた「血の通った解説」
単なる情報源の羅列では、AIに勝てません。
AIは情報源をもとにして情報を出してくれますが 、 AIが出してくれる文脈や感情は信用できますか?
多くの人はNOと答えるでしょう。下記は例題です。
- 例1:今日とあるイベント会場に行ってきて〇〇を見てきて感動しました。特に〇〇に関心を受けて、作者とお話する機会があり、作者いわく「〇〇と考えて作りました」。→この場でしか聞けない体験談がきける。興味分野が人によって参考になる。
- 例2:〇〇を購入しました。購入して実際に使ってメリットデメリットがありました。それぞれ〇〇です。→体験談に関して実際に使ってる人のほうが信頼性があがる。
人間が実際に感じたものは人間が書いた記事のほうが信用できます。
- イベントの記録と歴史的価値
「イベントの記録が、画像付きでまとめられ、歴史的価値をもたらす」種類の記事も、貴重な資産となります。
ふとした写真でも当時の風情がどんな感じなのか、その時に起きた事象が事細かく書かれていることが例に上がります。
たとえばゲームの歴史を振り返るとき、どんなゲーム機が発売されたのかという情報だけでなく、当時の経済状況でなぜそのコンセプトが開発されたのかといった背景や、開発者のふとした発言など、一次情報に近い記録こそが重要です。
今閲覧しても面白く、現代の販売戦略を考えるときにも参考になります。
これらの記事は、その時点での記録が、将来的に「歴史的資料」や「時代を理解するための文脈」を提供する、まさに「熟成する資産」となります。
情報の知名度とは
「知名度」は、発信者である私自身のパーソナルブランドに直結する価値です。
QiitaやNoteで注目を集めることはできますが、それはプラットフォーム内の人気です。プラットフォームを離れた瞬間に、あなたの名前は忘れ去られてしまうかもしれません。
しかし、ご自身のブログに読者を誘導し、そこで「このドメイン(ブログ名)には、あの人(私)の信頼できる情報がある」と認識してもらうことが、本当の知名度を築くということです。
知名度を資産として蓄積するには、以下の要素が必要です。
- 一貫性: 質の高い記事を、同じホーム(独自ドメイン)で発信し続けること。
- 信頼性: 誰もがコピーできる情報ではなく、独自の知見と考察で情報の正確性を担保すること。
最終的に、私の目標は、「QiitaやAIでは得られない、深い情報はこのブログにある」という認識を読者に持ってもらい、それがキャリアやビジネスに繋がる「個人の影響力」という名の資産を築くことです。
もし他のプラットホームもするのであれば、「YouTube」が良いですね。動画になるとベクトルが違ってきますが、音声にすることで文字や画像だけの表現方法だけでは出来ないことが伝えられます。
またYouTubeはアクティブユーザーも多く、再生回数やチャンネル登録数次第ではおすすめに乗りやすくなります。
「X」などのSNSは上手に活用したほうがいいです。またブログに誘導できるので流動性もあります。
改めて言いますが、ドメイン・ウェブサイトを持たないのは非常に勿体ないです。まだお持ちでない方は、ぜひこの機会に自己証明と資産構築の場を作りましょう。まだ作ってない人、クリエイター、企業などぜひアピール出来る人は是非作りましょう
QiitaやNote機能物足りなくない?
ぶっちゃけ自分で運用しているサイトはカスタマイズ性が無限大なので出来ることが多いです。
自動でSNS投稿したり、Googleアナリティクスで何が読まれているか一覧が見えたりなど。
特に運用する上でなんの記事が読まれていてリピータや滞在率がどれくらいあるか参考になってきます。
あとQiitaだと記事のアイキャッチ画像が作れなかったり、Noteだとコードブロックが使いづらかったりと難点があります。
有料記事にしたらいいのでは?
ずっと他のプラットフォームのデメリットばかり書いていたので、少しばかり褒めたいと思います。
Noteの良いところは有料記事が購入しやすいことでしょう。あの「頂きりりちゃん」もNoteで有料記事販売してたくらいです。知らないサイトで決済するのは不安ですが、多く使われているサービスなら安心して決済できますね。
有料記事は、単なる情報発信ではなく、ダイレクトに売上=期待値という形で現れるため、発信者にとって嬉しいインセンティブとなります。ある読者は単純に興味をもってくれたので購読、ある読者はファンなので投げ銭の意味で購読、色々ケースは考えられるでしょう。
しかし、そこで湧き上がってくるのが「自分の記事にどれくらい価値があるか」という疑問です。
有料記事のデメリット
有料にすることで、当然デメリットも発生します。
- 信頼性の喪失リスク: 質の悪い記事を有料にすれば読者が離れていき、クソ記事を書けば他の記事も購読しなくなる恐れがあります。これは、前述した「知名度」という資産を根本から崩しかねません。
- 検索流入の遮断: 文字が非公開なので、Googleなどの検索に引っかかりづらくなってしまいます。私自身は、できるだけ多くの人に見ていただきたいという思いから、一般公開をなるべくするという方針です。
このため、私の情報発信の軸は、手間と引き換えに大きなリターンを得る「独自ドメインでの一般公開記事」に集中させるという結論に至りました。
このブログが情報発信の「ホーム」である理由
私がQiitaやNoteへの投稿に価値を感じなくなったのは、決してそれらのプラットフォームの存在価値を否定するものではありません。
現代社会でAIが情報を瞬時に生成し、情報の価値が薄れてしまう現代において、「限られた時間と労力をどこに投下すべきか」という問いへの答えは明確です。
それは、「努力が永続的な資産となり、自分のパーソナルブランドに積み上がる場所」、つまりこのサイト(独自ドメインのブログ)です。
情報発信は、単なる「記事の公開」ではありません。それは、「未来の自分への投資」であり、「読者との長期的な信頼関係の構築」なのです。
これからも読者が楽しんで頂ける記事書きますのでよろしくお願いします!




